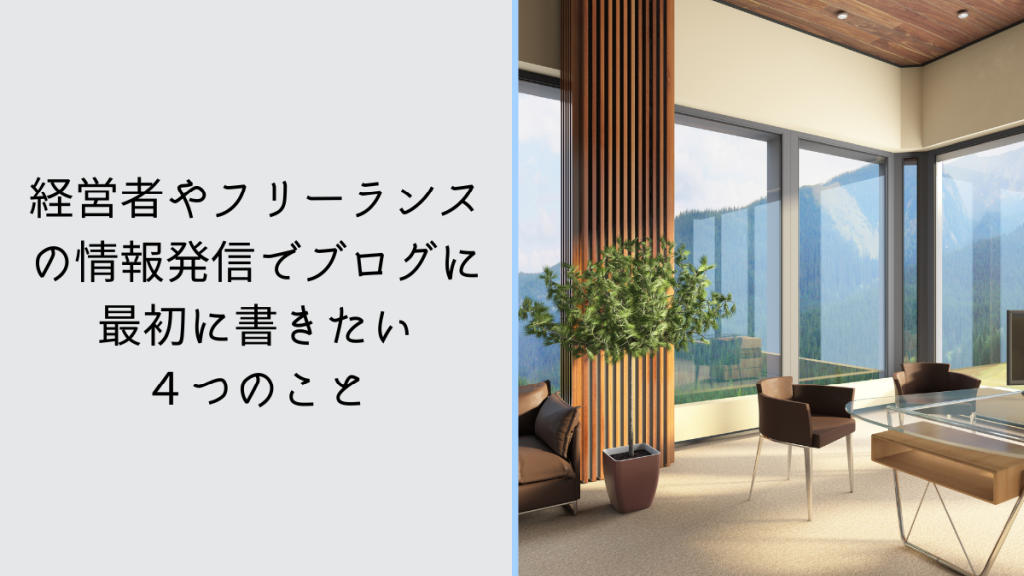個人事業主や経営者が発信し始めるときの、知っておきたい炎上対策

SNSやブログでの発信は、ビジネスの成長に欠かせない時代になりました。しかし、「炎上」のリスクは常に潜んでいます。私自身、会社の公式アカウント運用で危機を感じた経験があります。今回は、その経験も踏まえて、安全に情報発信を行うための実践的な対策をご紹介します。
もくじ
1. 実体験から学んだ炎上の流れと初期対応の重要性
SNSで炎上が加速するパターン
2. 発信前に知っておくべき基本的なリスク
3. とくに注意したい話題
炎上リスクの高い話題
写真の位置情報にも注意したい
4. 実践をおすすめするSNSの発信ポリシー
5. 炎上したときの対応フロー
6. 事前に作っておきたいガイドライン
まとめ:安全な発信のために
1. 実体験から学んだ炎上の流れと初期対応の重要性
企業の公式アカウントを運用していると、さまざまなことが起こります。自社アカウントを運用していた際に、一度だけちょっぴり炎上しました。その際は、すぐに社内のリスク管理委員会に相談し、以下の対応を取りました。
- 当社としての立場・考え方を明確に文書化
- 企業公式サイトの「お知らせ」ページで公式見解を発表
- 情報が切り取られて誤解されないよう、全文を画像化してSNSでも投稿
こういった迅速な対応により、炎上を未然に防ぐことができました。発生して当日のうちに対応したのでそれほど燃えませんでしたが、1~2日寝かせると炎上したであろうことが予測されました。目の前でどんどん拡散されていく様子は怖いと感じましたが、適切な対応をすばやく取れれば、鎮火できることもよくわかりました。
SNSで炎上が加速するパターン
SNSで炎上する際は、さまざまなケースがあります。次のような流れがあることを認識していただくと、どこで何が起こり、どこを鎮火する必要があるかを理解できます。SNSを運用する際は、この流れを頭の片隅に置いていただけるといいと思います。

- Instagram、YouTubeなどで投稿・コメントが問題視される
- その内容がスクリーンショットされX(旧Twitter)に転載される
- X上で「火事場見物」のように炎上を面白がるアカウントが拡散
- 元のコンテキストとは違う形で情報が広まり、収拾がつかなくなる
一度火がついてから炎上するまでは、半日ぐらいかかることが多いです。日中の投稿が少しずつ波紋を呼び、夜の間にコアユーザーに広がっていき、翌朝気づくと大炎上しているといったイメージです。
InstagramやYouTubeは、仕組み自体は炎上しにくいのですが、そこからX(旧Twitter)に情報が流れていって、一気に燃えることがほとんどです。始まりがX(旧Twitter)の投稿だった場合は、加速する時間がもう少し速いです。
2. 発信前に知っておくべき基本的なリスク
SNSの投稿は「一度投稿しても、削除すれば大丈夫」と考える方も多いですが、「一度投稿したら、瞬間投稿でも誰かが魚拓(※スクリーンショットの保存等)を撮っている」と考えたほうが、リスクは起こりにくいです。
おさえておきたいポイントは次の3つです。
- 一瞬でも公開したらずっと残ると考える
一度インターネット上に公開された情報は、削除しても完全に消すことは困難です。スクリーンショットやアーカイブが残る可能性を常に意識する必要があります。 - 「切り取り」による情報操作
SNSの投稿は、悪意を持って切り取られ、文脈が変えられる可能性があります。私は「火のない所に煙は立たぬ」の精神で、少しでもリスクになる発言は避けるようにしています。 - 悪意の存在を前提とする
こちらに悪意がなくても、相手に悪意があると簡単に炎上します。この前提で発言することが重要です。
3. とくに注意したい話題
炎上リスクの高い話題
以下の話題はとくに炎上リスクが高いです。
- 高級品や高級レストランなど、金額がわかる投稿
- 会社や仕事での出来事(とくに不満や批判)
- 上司、同僚、クライアントに関する内容
- 政治、宗教、ジェンダーなどセンシティブな話題
自分のサービスを知ってもらうためにX(旧Twitter)の運用を始めると、「1日最低1投稿。できれば5投稿できるとベスト」などと私のようなSNSコンサルが言いますので(すみません)、投稿ネタを増やすために、出かけた先の映えショットを投稿しようとする方もいらっしゃいます。
たとえばラグジュアリーホテルにお勤めとか、ラグジュアリーブランドのPRの方で、業務上必要な場面であれば問題ないのですが、そうでない場合は投稿をおすすめしません。とくに高額のものについては、金額の多寡が見えるといらぬ妬み嫉み(ねたみそねみ)を呼ぶことがあるためです。
その金額がネタとしておもしろいとか、誰が見てもハッピーな気持ちになるとか、そういう要素があれば問題ないのですが、たいていの場合は逆効果になります。
また、業務に関する不満や批判は厳禁ですし、政治・宗教・ジェンダーに関するセンシティブな話題もできるだけ避けたいところです。
写真の位置情報にも注意したい
もうひとつ気をつけたいのが、写真の位置情報です。スマホで撮影した写真には、位置情報が含まれていることがあります。「カメラ」アプリのプライバシー設定で、撮影した写真に位置情報が添付されていると、どこで撮ったかが克明にわかります。ですので、SNSに投稿する写真をスマホのカメラで撮影する場合は、「カメラ」アプリは必ず位置情報を切ります。
Instagramは、最近アップデートされて「地図」位置情報表示がデフォルトで「オン」になっています(2025/4/11現在)。必ずオフにしましょう。
※参考:Instagramの新機能「地図」でフォロワーに“家バレ”しない設定方法は?
4. 実践をおすすめするSNSの発信ポリシー
そういうわけで、以下がSNS発信にあたっての基本原則です。

基本原則
- 誰かがいやな思いをする投稿はしない
- 会社や仕事の内部事情は一切書かない
- ネガティブな話題、人の悪口は投稿しない
- 高額商品、高級レストラン、高級ホテルなど、金額が波紋を呼ぶような投稿は避ける
これらは、一見あたり前のようですが、「つい」うっかり書いてしまいがちな内容ですので、しかと心に留め置いていただけたらと思います。これさえ守っていれば、炎上はほとんど起こりません。
もちろん、誰かのリプライにコメントする際も、この原則は適用されます。リプライ欄が、燃えますので。
5. 炎上したときの対応フロー
とはいっても、燃えるときは燃えます。その場合の対応のしかたを事前に考えておくと、安心です。対応のしかたはシンプルです。
- 慌てないこと
- できるだけ早期に対応する
- 公式サイトや公式アカウントに文書画像等で公式文書を出す
- 切り取られて情報操作されないよう、全文を提示する
- 事実関係の誤認があるか
- 実害が出る可能性があるか
- 社会的責任を果たす必要があるか
事実関係に誤認がなく、実害がない。かつ、社会的責任を果たすにあたってやるべきことをできている場合は、無反応戦略を取ることができます。そうでない場合は、適切な対処を必要とします。
6. 事前に作っておきたいガイドライン
SNS投稿を始めるにあたって、炎上にリスクを感じる場合は、こういったガイドラインをつくることをおすすめします。これがあるとなにかあったときにおろおろしなくて済みますし、炎上を最小限で食い止めやすくなります。慣れるまでは、毎回確認するのもおすすめです。

投稿前に、以下の項目を確認します。
- この投稿で誰かが不快になる可能性はないか
- 個人が特定できる情報は含まれていないか
- 切り取られても問題ない内容か
- 金額や価格が特定できる内容が含まれていないか
- 位置情報は含まれていないか
- 信頼できる専門家(弁護士、SNSコンサルタント等)の連絡先をもっておく
- 炎上時の対応フローを事前に決めておく
- 過去の投稿のスクリーンショットを保存(発言が改変された場合の証拠として)
また、インターネット上の誹謗中傷等については、警察庁や総務省から対応策や対応法令なども施行されており、誹謗中傷を受けた場合は対策を取ることもできます。こういった対応もあると知っておくことで、自分で自分の身を守ることもできます。
※参考:インターネット上の誹謗中傷等への対応
※参考:情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)とは?
まとめ:安全な発信のために
SNSでの発信は、ビジネスチャンスを広げる一方で、リスクも伴います。15年ほどSNSを使ったり、運用している経験から言えることは、「予防」が最も重要である点です。
- 発信前に必ずリスクチェックを行う
- 炎上しやすい話題は避ける
- 万が一に備えて対応フローを準備しておく
SNSは本来、人とつながり価値を共有するすばらしい、そして楽しいツールです。適切な対策を講じることで、安心して情報発信を続けられます。不安がある場合は、事前対策をしっかり行い、適度に怖がりながら、使いこなしていただけたらと思います。



-1.png)